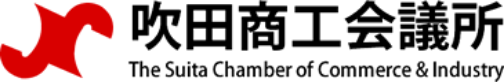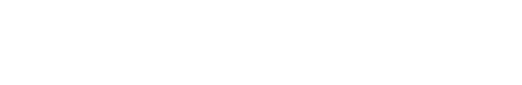2026年度理事長所信
違いを知り、共に生きる
【はじめに】
2025 年、大阪・関西万博が開催され、日本各地、世界各地から多くの人が、この大阪の地に訪れました。
その半世紀以上前の1970 年、吹田でアジア初の万博が開催された年に、吹田青年会議所は誕生しました。
当時の吹田は高度経済成⾧期や万博に伴う都市整備の影響もあり、約10 年間で人口が倍増するという現代の私たちにはイメージできないような状況にありました。
急激な人口増加に伴う教育設備、保育設備の不足、高度経済成⾧に伴う公害問題等、今とは異なる問題を抱える吹田で、先輩諸兄姉は時々のまちの課題に向き合いながら当会の活動を繋いできてくださいました。
だからこそ、今日の吹田青年会議所は行政や地域団体から信頼されながら、多くの会員と共に活動を続けることができています。
青年会議所に所属する会員はその全員が「明るい豊かな社会」の実現を目指して日々活動しています。
では、「明るい豊かな社会」とは何でしょうか。
現代社会において、数十年前より人々の「幸せ」は多様化しています。
今まで当然と思われたライフスタイルは明確に若者たちから拒絶されています。
晩婚化、少子化が進み、子どもを持たない選択をとる人も増え、家族のあり方は大きく変わってきています。
今まで男女で区別されていた性は多様化しました。
終身雇用の時代は終わり、個人で働く人、複数の仕事を持つ人が増えました。
キャリアの多様化に伴い、社会人の学びなおしニーズも高まってきています。
また、自身のアイデンティティを大切にして生きたいというニーズも高まっています。
しかし、社会はソフト面でもハード面でも十分にその変化を受け入れる準備ができていないように思います。
ダイバーシティーやインクルージョンといった言葉がビジネスの場や政策において多く使われるようになり、多様性のある社会については多くの人が意識するようにはなりました。
その反面、それぞれの文化的・社会的背景と相反する価値観に困惑し、拒否し、時には排除する動きがあることは事実です。
また、新しい社会制度の設計も追いついているとはいえません。
「明るい豊かな社会」について、人それぞれイメージすることは違うでしょう。
ただ、まずは人々が異なる価値観を持ちつつも、それぞれが自らの幸せを肯定的に追求できる、それが「明るい豊かな社会」のスタートラインではないでしょうか。
当会も従前の常識を時代に先駆けてアップデートしていかなくてはいけません。
そして、誰もが互いの違いを知り、違いを認め、その上で共生していく社会となるよう活動してまいります。
【子どもたちの異なる背景に寄り添う青少年健全育成事業】
吹田青年会議所は毎年のように青少年健全育成事業を実施し、市民の皆様から大変好評をいただいております。
募集を開始した当日には募集枠が全て埋まり、お断りをしてもキャンセル待ちをしたいとの声をいただくことがあるほどです。
この現状は有難いことであるものの、親が子どものために募集開始日に待ち構えて応募の手続きをしてくれる、そんな「恵まれた子どもたち」しか参加できていないという問題をはらんでいます。
青年会議所の行う青少年健全育成事業は単なるイベントではなく、青少年の持つ課題に対し、それを解決するために仮説を立て、手法を組み立て、実行していくものです。
そうなると当然、私たちが想定する事業対象者となる子どもは、漠然とした「子どもたち」ではなく、もっと具体的な「なんらかの課題を持つ子ども」となるべきです。
当会の青少年健全育成事業が多くの方に支持されているからこそ、課題感を今一度明確にし、対象となる子どもに届く事業を構築してまいります。
人材育成はまちにとって大きな課題です。
明るい豊かな社会の実現のためには、子どもたちに平等にチャンスがあり、子どもたちが生き生きと未来を語れる社会が必要です。
日本では、今、子どもを取り巻く環境は大きく変わっています。
教員の働き方改革、担い手不足によって部活や宿泊行事、学校行事の簡素化が進んでいます。
今まで地域の子どもに様々な機会を提供していた地域団体も活動を縮小しているところが多くなっています。
このような背景のもと、子どもたちの体験格差は開くばかりです。
当会は、様々な背景をもつ子どもたちにきっかけを提供できる、そんな団体であり続けたいと思っています。
【異なる団体と協働するまちづくり運動】
吹田青年会議所は、地域のより良い未来を創るために活動している団体です。
吹田のまちは、住みたいまちランキングでも上位をとるほど、人気のあるエリアで人口も増え続けています。
他方、防災や教育、世代間交流、今後の人口減少に対する準備等まちの課題は多くあります。
そのなかで、四十数人の当会会員だけでできることには限りがあります。
私は青年会議所活動を始めて以降、「明るい豊かな社会の実現」と謳うのであれば、まずは自身の所属しているコミュニティの活動をよく知り、足元の社会を良くしなければいけないと考え、青年会議所活動以外にも色々な地域の活動に参加してきました。
保護者会、PTA、自治会、学校評議員等そこで得た経験、人脈、知識は私の青年会議所活動の糧になっています。
数年前、私は設営側で地域の餅つき大会に参加しました。今までよくある年末の地域行事くらいにしか思っていませんでしたが、地域倉庫に大量の炊き出しができる設備が保管され、地域の各団体が連携をとり、数百食のお餅が短時間で手際よく準備されていく様は、まさに災害時の炊き出し訓練ともいえるようなものでした。
このような地域活動が、きっと有事の際には地域の大きな力になるだろうと感じました。
三十年以内に高確率で南海トラフ巨大地震が発生し、吹田も多くの被害を受けると言われています。
それだけではなく、上町断層など、直下型地震によって南海トラフ巨大地震以上の被害を受ける可能性もあります。
吹田青年会議所は、このような予測を受けて防災について定例会で学び、常に防災意識を高めてきました。
しかし、実際に今、巨大地震が起きたとき、私たちは瞬発力をもって十分に動くことができるでしょうか。
災害時に限らず当会だけでできることは、限られた小さなことでしかありません。
行政、地域団体等を巻き込み、活動に賛同してくださる方が加わってこそ、初めて運動の輪が広がり、社会活動へと発展していくのです。
地域には私たちがまだかかわりを持っていない団体がたくさんあり、それぞれの団体は大きな可能性と力を持っています。
吹田青年会議所は地域団体との連携強化を中⾧期ビジョンにも掲げています。
地域団体との連携を強化し、事業などで、連携、協働することにより私たちのまちづくり事業はより多くの人に届くことでしょう。
当会がまちづくり運動をする際には、その背景を精査し、事業内容を練り上げるのと同じくらい、誰と活動するか、誰に協力いただけるか、より社会にインパクトを与えるためには誰の助けが必要かをもっと考えなくてはいけません。
【会員の意識を引き上げる研修事業】
現在、吹田青年会議所は約6 割の会員が入会3 年未満となっています。
また、入会2年目から理事を引き受けるということも多くなりました。
今年度は実に5 人の委員⾧のうち4 人が新任委員⾧という体制になっています。
よく言えば、新陳代謝が早く、若手でも意欲さえあればどんどん意思決定側に回れる団体ではあります。
しかし、青年会議所の理念を組織に浸透させ、全員が同じ目的意識を持たなければ、組織は強くなりません。
青年会議所は、どんな大きな会社の社⾧でも、入会直後は等しく新人会員として現場で色々な役割を割り当てられる団体です。
自分の今行っていることが、誰のために、どういう目的で行われ、どのように実を結ぶのかがわからず、困惑することも多いと思います。
目的意識、問題意識があれば、単純な仕事ひとつをとっても動き方が変わってくるはずです。
会員一人ひとりの意識が吹田青年会議所の活動の価値を高めていきます。
だからこそ、会員全員に青年会議所の理念を浸透させ、日々の青年会議所活動の意義を一人ひとりが理解している状況を作ることが何よりも大事になってきます。
当会は、今までも大阪ブロック協議会で開催される研修事業に積極的に参加を促すなどして理念の浸透に力を入れてきました。
しかし、どうしても当会以外で行われる研修では参加率が下がり、また参加する会員が固定化しがちなどの問題点があります。
どれだけセミナーの内容が良くとも、多くの人が参加しなければ、その効果は限定的になってしまいます。
また、セミナーに参加したことがない会員はどれだけ勧められても、どう良いのかピンと来ないというのが正直な気持ちだと思います。
よって、多くの会員が参加しやすいセミナーの開催を検討し、そこで学びを得た会員が次の研修に主体的に動き出す、そのような場を作ることが重要だと考えています。
【異なる問題意識と価値観に触れる定例会】
私は毎月の定例会こそ、青年会議所活動の根幹であると考えています。
当会の会員全員が、毎月原則18 日に行われる定例会への出席を約束して入会しています。
また、運営規定でも定例会への参加が義務付けられています。
明るい豊かなまちづくりを目指して活動する上で、社会が抱える問題点に常にアンテナを張り、未来を見通し、私たちがすべきことは何かを考え続けることが必要です。
近年ソーシャルメディアの台頭により、私たちの情報収集の態様は従前と大きく変わってきました。
自身の閲覧履歴やリアクションの記録からレコメンデーションされた情報に接している時間が格段に増えました。
結果、自身の興味のある分野に関しては情報が大量に入ってくるものの、興味のない分野については、従前以上に目にする機会が減ってしまいました。
さらに主義主張が対立するテーマについては、自身の共感する意見ばかりが自身のタイムラインに流れてくるようになり、あたかもその意見が多数派であるように錯覚するという弊害も起きています。
情報化社会ゆえ、色々な情報を素早く大量に手に入れることは容易になったものの、意識しなければ我々が接する情報は非常に偏ったものとなってしまう恐れがあります。
だからこそ、定例会で専門家の方や経験者の方から、正しい生の情報を得ることが重要になってきます。
定例会で学んだことが私たちの血肉となり、事業を実施する際に花開き、より良い社会の実現に繋がります。
だからこそ、私たちに何が足りないかを見極めて定例会を設える必要があります。
また、私は青年会議所の魅力は、仕事も、家庭環境も、政治的主張も、宗教観も、あらゆることが異なる人間が集まることだと思っています。
異なる人間が集まるからこそ、新しい学びや発見が生まれ、自分だけでは到底接することのなかった世界に接することができます。
定例会を始めとする議案構築においても、たくさんの異なる視点があることによって、より多角的観点をもって学びを深めることができます。
【異なる地域、団体での学びと友情】
他者を知らなければ、自分がどのような者なのかを知ることはできません。
他を知り、違いを認識してこそ、自身の良い点、悪い点が見え、自身の輪郭がはっきりしていきます。
青年会議所には近隣LOM、友好LOM、姉妹LOM との交流、大阪ブロック協議会、近畿地区協議会、日本青年会議所による各種大会等、また、それら団体への出向など、吹田青年会議所以外のJAYCEE とかかわる機会がたくさん用意されています。
それらの活動を通じて、大阪の中での吹田、日本の中での吹田を認識し、まちの問題点や特徴、可能性を知ることができるものと考えています。
また、そこで得られる友情は何物にも代えがたく、吹田青年会議所以外にも相談する仲間がいる、一緒に笑える仲間がいるということは青年会議所活動をより充実したものにするはずです。
また、当会は先輩方が活動を積み重ね、信頼されてきたからこそ、吹田市をはじめとする市内の多くの団体から出向の機会をいただいております。
地域団体への出向は青年会議所活動とは異なる切り口からまちとかかわることができる機会であり、また地域で活動する団体や人々と知り合う大切なきっかけでもあります。
多くの会員が出向や各種大会への参加を通して、外に目を向けることが結果として吹田のまちの発展に寄与するものと信じています。
【異なる背景に配慮した会員拡大】
多くの仲間がいることは青年会議所運動にとって、とても大事なことです。人数が減少すれば、おのずと私たちの活動にも制限がかかってしまいます。
また、新しい人材は組織の新陳代謝を促すものであり、常に時代の先を見据えて活動する私たちに必要不可欠なものです。
去年多くの新入会員を迎えることができたこともあり、本年度は例年に比べて多くの会員で1 年のスタートを切ることができました。
しかし、吹田の人口規模からして、まだまだマンパワーが必要です。
残念ながら、青年会議所は対象世代の人口減少のスピード以上に会員を減らしています。
この背景には従前の青年会議所活動が、現代の青年層のライフスタイルと合わなくなってきたということもあると考えています。
総務省の統計によると、30 代の共働き世代は約6 割にのぼり、ここ10 年間でその割合は2 割以上増えています。
結婚年齢、出産年齢の高齢化もあり、青年会議所活動を支えていた層の人たちにも家事育児の負担割合が増えた結果、青年会議所活動への参加をためらうことも多いのではないかと思います。
私たちは同志を増やすとともに、志さえあれば、会社勤めの人であっても、夫婦共働きの家庭の人であっても、小さい子どもを育てる人であっても、様々な人にとって参加しやすい会を作っていかなくてはなりません。
現代技術を活用し、簡略化できる部分は簡略化し、負担を減らし、本質的な活動に時間を割ける、そのような団体づくりをすることが⾧期的には会員拡大に繋がっていくと考えています。
私は会員拡大において、人数のみならず、多様な人材が増えるということが重要な要素の一つであると考えています。
JC 宣言文にもあるように、我々は「輝く個性が調和する未来」を目指しています。
そのためには、まず会自体が多様なバックグラウンドを持つ者同士、切磋琢磨し、社会の様々な層の意見を反映する素地を持つことが必要です。
【おわりに】
私は2016 年に入会し、入会から丸10 年が経ちました。
当時0 歳の⾧女を育てながら入会し、その後活動を続けながら⾧男を出産した私にとって、青年会議所でのこの10年間はできないこと、迷惑をかけてしまうことも多く、自分の不甲斐なさを歯がゆく思うことの連続でした。
最近でこそ子どもを連れて参加する会員も増えてきたものの、入会当時はそのような文化もあまりなく、子育てをしながら活動する女性会員も多くはありませんでした。
そのような状況でしたので、理事⾧などはおろか、青年会議所で無事に卒業の40 歳を迎えられることすらイメージできませんでした。
そんな私を支えてくれたのは多くの先輩方や仲間たちでした。
仲間たちは常に私がおかれた環境を理解し、どうすれば参加できるかを模索し、一緒に活動することを諦めないでいてくれました。
私はそのような先輩方と仲間たちから、違いを受け入れる勇気、諦めない強さ、時代と共に変化するしなやかさを学びました。
青年会議所は人種、性別、宗教、仕事、家庭環境等一切の事情を問わず、20 歳から40 歳までの明るい豊かな社会を目指す青年経済人が入会できる多様性に富んだ団体です。
これこそが、青年会議所のエネルギー源であると私は考えています。
様々な背景を持つ人たちと共に、それぞれの人が持つ違いを深く知り、お互いにその違いを認め、そのうえで共生していく、それが私の目指す青年会議所活動であり、社会の姿です。
本年はその目標を胸に、会員一丸となって走ってまいります。
<基本方針案>
◆必要な子どもに届く青少年健全育成事業
◆他団体と共に創るまちづくり事業
◆価値観を共有し、活動を加速させる研修
◆社会への問題意識を持った例会設営
◆時代に応じた会員拡大
◆多様性を認め合う組織風土の醸成
◆責任感ある理事会運営